健康コラム君津健康センターの医師・スタッフから、
香りの効用
皆さんは寝る前にしている習慣はありますか。私は寝る前に頭だけ冴えてしまい、上手く寝つけないことがあります。寝る前は子供と一緒に絵本を読んだり穏やかに過ごせればいいですが、家事やら支払いやらすべきことに追いたてられていると、頭の切り替えがうまくいかないことがあります。


何かいい方法ないかと考えて思いついたのが、精油を用いた芳香浴でした。精油をティッシュペーパーやハンカチに数滴たらし枕元に置くだけです。芳香浴はディフューザーがないとできないと思い込んでおり、ディフューザーは音や光が出るものや種類も多く、選んだり管理したりするのも面倒だしかえってリラックスにならないではないか!と敬遠していました。ただ、手軽な方法があると知り、思い立ってやってみることにしました。
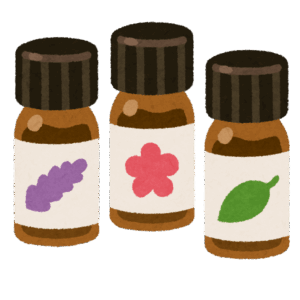
最近は精油を販売している店舗も多くなったので、店頭で眠りに効果があると言われているものを嗅いでみて、ラベンダーとイランイランを使用してみました。香りに感覚を集中することで頭を思考が駆け巡ることも治まり、快適に眠りにつけるようになりました。毎日どちらか好きな香りを選んで使用するので、飽きずに楽しく続けています。
*・*・*・*
香りの効果をというと「アロマテラピー」という用語が頭に浮かびます。「アロマテラピー」という用語は、「芳香・香り」を表す「アロマ(aroma)」と「治療・療法」を表す「テラピー(therapy)」を組み合わせた造語で、1937年に発刊されたフランスのルネ=モーリス・ガットフォセによる著作において用いられました。ガットフォセはフランス・リヨンで香料会社の経営者であり、香料の研究を行う化学者、調香師でもあります。実験中の爆発事故でやけどを負った際、香料が身近にあり伝承療法の中で精油が用いられることを知っていたため、ラベンダー精油を熱傷治療に用いて効果を実感しました。それをきっかけに、ガットフォセは精油の「治療」としての側面を科学的に体系化することに尽力したそうです。その後、フランスの医師たちが医学的な考察を加え、アロマテラピーが精油(=植物の成分)を薬剤として外用・内服する医療行為として確立していきます。更にイギリスの看護師 マルグリット・モーリーが看護現場で行われるマッサージケアに精油を応用したことで「ケア」としての側面が加わり、触覚・嗅覚からの効果が言及されるようになります。
私はアロマテラピーというと医療行為より美容分野を思い浮かべていました。日本ではアロマテラピーが「芳香療法」と訳されること、日本にはイギリスからアロマテラピーが伝わったことなどが理由にあるようです。
*・*・*・*
香りの研究はここ30年ほどで急速に進んでおり、睡眠やストレスへの効果などだけでなく、認知症の予防や治療など様々な分野での応用が期待されています。安全性への配慮は必要ですが、動くことができない植物が自身のために持っている力を、精油を通してもっと気軽に借りてみてもいいかなと思いました。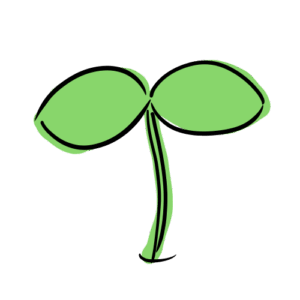

「健康さんぽ107号」
※一般財団法人君津健康センターの許可なく転載することはご遠慮下さい。




